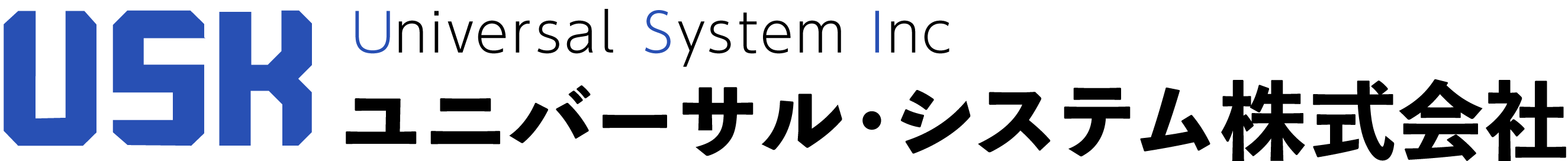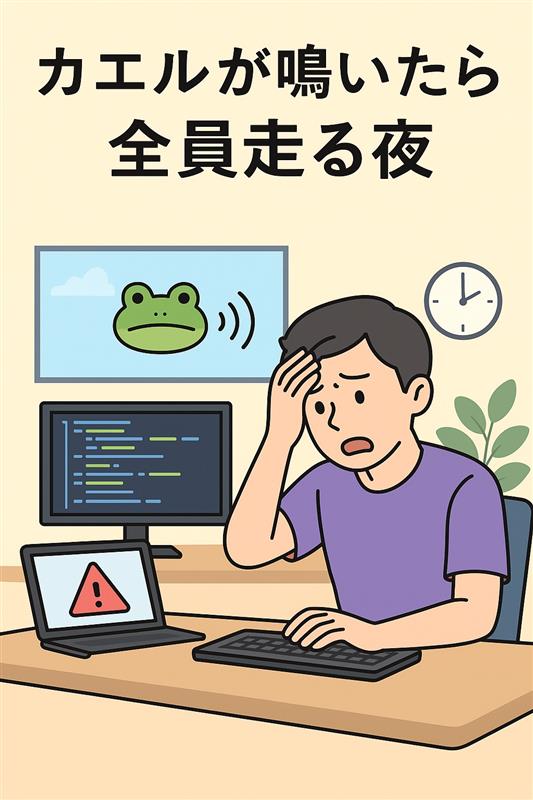
21時12分。
「ルパン三世のテーマ」が社内スピーカーから流れ始めた。
この曲が鳴ると、誰もが“今夜のデプロイ”を意識する。
僕は手のひらの汗をズボンで拭いながら、Enterキーを押した。
10分後。
Slackのモニターに、カエルの鳴き声が響く。
社内監視ツール「FrogWatch」が異常を検知した瞬間だ。
鼓動が一拍飛ぶ。背筋に冷たいものが走る。
エラーの原因は、僕が追加した機能のAPIレスポンス処理。
条件分岐ひとつの想定漏れで、ユーザーのダッシュボードが真っ白になっていた。
周りの席が一斉に動く。
バックオフィスのHさんまで、モニターに向かってSQLを叩き始める。
「影響範囲、テーブルのこことここと…あ、これも該当だわ」
彼女の声で、処理対象が一気に絞られていく。
画面越しに集まったメンバーは9人。
誰も責めない。代わりに短く早口でコマンドが飛び交う。
手元のキーボードは汗で滑る。
復旧完了の合図を打ち込む指先が、やけに重かった。
21時47分。
サービスが安定し、再びルパンのサビが流れ出す。
Slackには「おつカエル!」のスタンプが連打される。
椅子にもたれた瞬間、やっと呼吸が深くなった。
この会社では、カエルが鳴けば誰でも走る。
それが、3年経っても僕がこの現場から離れられない理由だ。
…と、ここまで読んでいただいたこの文章、実は生成AIが書いたサンプルです。
最近、生成AIで色々試すのにハマっています。
ちなみに記事を書く際、AIに与えた指示は三つ
1.入社3年目のITエンジニア視点
2.変な社内の文化がある
3.障害対応の緊迫感と臨場感
これらを指示しただけで、数秒後にこの文章が生成されました。
同じようなやり方で、他のエピソードや文化も即座に文章化できます。
びっくりしますね。
しかも、AIはまだまだ進化中。
どこまでできるようになるのか、いつかは人間の知性を越えるのか。
そんなAIをどう使っていくのがいいのか。
未来に期待を馳せながら、今日もAIを仕事に活かす方法を模索しています。
あ、冒頭のイラストもAIの生成ですよ。